第七話 黄金の雷(6)
そして、双方の被害も、また、共に言語を絶する甚大さであった。
その日の戦闘で、負傷した者、命を落とした者の数は計り知れず、戦場となった大地の上には、褐色や白色の無数の亡骸(なきがら)が、その肌を血まみれにして、あるいは、焼け焦げて累々と横たわり、まともな神経では、とても目を向けられぬ惨状である。
インカ軍の指令本部では、トゥパク・アマルや側近たちが、被害状況の把握と負傷兵たちの救護のために、昼間の決戦で痛めた己の翼を休める間など一寸も無いめまぐるしさで、懸命に活動を続けていた。
ところで、負傷兵の看護に当たる者たちの中には、いつものように、かのコイユールの姿もあった。
数知れず次々と運び込まれる兵たちに、今や、その自然療法の力を軍内でも認知されるに至っていた彼女は、状態の重い兵たちの元に呼び出されては、次々と引き回されるように移動し、その療法を施していく。
全ての力を出し切り、もはや己の身も心も切り落としながら負傷兵たちにそれらを与えて回っているかのごとくの彼女は、すっかりやつれかえり、とても18歳の若い娘には見えぬような相貌になっていた。
それでも、彼女は、ひとつも惜しむことなく、己のもつ全ての力を注ぎ続ける。
「リマの褐色兵」の将フィゲロアが亡くなった…――その噂は、コイユールのような治療場の女性たちの間にも、既に伝わっていた。
止血用の布を巻いた負傷兵の傷口に手を添えるコイユールの目元から、いつしか涙が溢れて、幾筋も頬を伝って流れ出した。
(え…?
私…フィゲロア様に会ったこともないのに……)
実際、常に治療場を持ち場とする彼女は、これまで一度も戦線に出たことはなく、フィゲロアに会うどころか、遠目から見たことすらなかった。
コイユールは己の反応に戸惑い、目の前に横たわる負傷兵に気付かれぬよう、慌てて涙を拭(ぬぐ)う。
しかし、彼女の意識を超えて、もっと深いところから突き上げるものを止められず、こらえようとすればするほど、かえって、その目からは涙が零れ落ちた。
(フィゲロア様…)
負傷兵の傷口に添えた自分の手に落ちる涙の粒を見つめながら、コイユールは心の中で、小さくその名を呼んでいた。
フィゲロア様…――。
スペイン側を信じていた最初の頃はともかく、次第に真実に目覚めていく中で、それでも同族のインカ側に刃を向け続けたその心境は如何なるものであったろうか?
そして、やっとトゥパク・アマル様の元で戦う決意をされたのに、あんなふうに亡くなられてしまうなんて…。
負傷兵に添えられたコイユールの指先は、すっかり冷たくなって、震えている。
(フィゲロア様…スペイン軍の配下にいたご自分の兵たちを、安全に、確実に、トゥパク・アマル様の元に行かせるために、今日の戦場でのタイミングを待っておられたのではないかしら…?
はじめから、ご自分の命と引き換えにする御覚悟だったのでは……?)
戦(いくさ)のことはもとより、武人の心境など、自分には察しようもないと、そう分かっていながらも、コイユールの心は何か納得できる答えを懸命に探し出そうとでもするかのように、果てしなく巡り続けた。
もう完全に涙に霞んだコイユールの視界のむこうで、そんな彼女に手を添えられていた負傷兵が薄く瞼を開け、苦しげな息の下から静かに語りかけてくる。
「君…わたしは、だいぶ痛みもとれてきたから、少し休んできなさい」
「あ…」
コイユールはハッとして、再び、急いで手の甲で涙を拭き取ると、「いえ!すいません…大丈夫です」と、慌てて負傷兵の前で姿勢を正した。
負傷兵は、僅かに首を振る。
「こんなに大勢の負傷兵を次々と診て、大丈夫なはずがない。
君たちのように看護してくれる者たちが参ってしまったら、この先、誰が怪我人の面倒を見る?」
「でも…」
「いいから、少し休んできなさい。
わたしは、少し眠っているから…」
「すいません…それでは、少しだけ…」
コイユールは申し訳なさそうに頭を下げると、その場を立って、随所に無数に横たわる負傷兵の傍を慎重にすり抜けながら治療場を出て行った。
治療場は、幾つかのテントを中心に、屋外にも広い治療スペースを保有している。
日中は、それら屋外のスペースも治療のために利用しているが、今の夜間は、秋の夜の冷え込みから逃れるように、全ての負傷兵はそれぞれの重傷度に応じたテントの中に収容されていた。

コイユールは治療場の敷地から少し離れた草地に入ると、放心したように、大木に背をもたれかけた。
昼間の戦闘によって傷ついた大地を労(いた)わるように、その地表をそっと撫でながら、秋の涼風が吹き過ぎていく。
その風に乗って流れ来るのだろうか、ひんやりとした夜の空気に漂う微かな血の臭いが、彼女の心をいっそう締め付ける。
コイユールは、再び溢れ出す涙を流れるままに、暫し、その姿勢のままでいた。
やがて涙も涸れると、コイユールは、少しずつ霞みの晴れてきた視界を確かめるように周囲を見渡す。
ふと前方を見ると、本陣の司令本部となっているトゥパク・アマルの館が目に入った。
彼女の心臓が、ドクンと、一度、大きく波打った。
「フィゲロア様」という大軍の将の死は、どれほど上の立場にある者でも死すことがあるという、当たり前かもしれぬ現実を現実のものとして、彼女に突き付けてくるものだった。
その意味でも、コイユールにとって、フィゲロアの死は非常な衝撃であったのだ。
既に、もう、かなり夜も更けていたが、本部となっている館の一階にも、トゥパク・アマルの家族が暮らす二階にも、まだその窓に灯りが点っている。
「トゥパク・アマル様…」
声にならぬ声で囁くと、コイユールは胸の前で、細い指を握り締めた。
今は、あの館の中に、トゥパク・アマル様はおられるのだわ……。
明日の夜も、また、あの館の灯りの中に、トゥパク・アマル様がいてくださいますように…――。
無意識のうちに、そんな言葉が胸の中をよぎっていった。
「あ…やだ…私ったら…!
そんなこと、当たり前じゃない。
明日だって、明後日だって、この先もずっと…!!」
コイユールは自分の想念を振り払うようにして、頭を振った。
そして、気持ちを切り替えようと、くっきりとしたその目元に力を宿して夜空を見上げた。
そんな彼女の視線の先では、ちょうど厚い雲が割れて、月の姿が雲間から現れてくるところであった。
その瞬間、コイユールの目が、ギョッとしたように、険しく見開かれた。
(あれは…――!?)
彼女の横顔が、凍りつく。
上空を見上げたまま、愕然と凝固しているコイユールの視界の中で、雲間から現われた月…――それは、まるで滴るような生々しい流血の色そのままに、どす黒い赤色だったのだ。

(お月様が、血の色に……!!)
突如、足元の大地が崩れていくような激しい錯覚に襲われ、思わず、コイユールの体がぐらついた。
その瞬間、現実の風景は全て消え去り、彼女の意識は吸い込まれるように、宇宙空間の中に放り出されていた。
そして、目の前には、煌々と輝く黄金色の太陽がある。
コイユールは、その光景に、すぐさま直観した。
(ああ!!
これは…まさか…あの時の…――!!)
全身を震わせて宙に佇むコイユールの前に、フラッシュバックしようとしている光景は、まさに彼女の予測通り、かつてトゥパク・アマルの治療中にトランス状態の中で垣間見てしまった、あの予見的ヴィジョンと全く同じものであった。
衝撃の眼をわななくように見開くコイユールの前で、黄金色に輝いていた太陽は、みるみる赤黒く変色していく。
そのまま、溶岩が溶け出すかのように、その赤黒いものはドロドロと液状に変容したかと思いきや、いきなり、轟音と共に、まるで彼女に襲い掛かるかのようにして迫り来るではないか…――!!

「!!!」
コイユールは咄嗟にしゃがんで、頭をかかえ、全身に覆い被さってくる大波の衝撃から逃れようと身を固めた。
巨大な荒波のように己を呑み込み荒れ狂う渦中で震えながら、彼女は、それが過ぎ去るのを必死に待った。
それが、決して実体のある現実のものではないことを、コイユールは悟っていたのだ。
そして、彼女の予測通り、激しい波が全て通り過ぎると、辺りは急速に静寂の中に戻っていった。
やがて、少し離れた所では治療場から流れ来る馴染みある音が聞こえ、野営地の方向からは、兵たちの話し声が風に乗って聞こえてくる。
現実の感覚が戻ってきたのだ。
しかし、コイユールは、先ほどの「波」をやり過ごすために地にしゃがみこんだ姿のまま、呆然として動けずにいた。
全身が痙攣するように震え、上下の歯が、ずっと遠くまで聞こえるのではないかと思われるほどガチガチと鳴っている。
コイユールは、冷たい草の上についていた震える両手を、激しく握り締めた。
(トゥパク・アマル様…――!!)

一方、その頃、トゥパク・アマルは陣営の司令本部となっている館の二階にある己の書斎で、一人、非常に険しい表情で机に向かっていた。
まさに、コイユールが先ほど視線を向けていた部屋の一つに、彼はいたのだ。
机上の燭台の下には、彼が今したためたのであろうか、数枚に渡る書状らしき文書が置かれている。
燭台の灯りに照らし出されるその鋭利な横顔には、ただならぬ緊迫感と決意が宿る。
トゥパク・アマルはいつにも増して真剣な眼差しで、複数回に渡ってその文書を読み返すと、再びペンを取り、傍に用意してあった豪華な装丁の封筒に、その流麗な文字で宛名を記入しはじめた。
蝋燭の溶け出す微かな音と、彼がペンを走らせる音だけが、静寂の中に響く。
そして、彼がちょうど宛名を書き終わるタイミングと合わせたかのように、書斎のドアにノックがした。
トゥパク・アマルはそのノックの音に顔を上げると、一瞬、躊躇(ためら)うように一呼吸おき、しかし、すぐに意を決した表情になって「入りたまえ」とドアの方に声をかける。
書斎のドアから姿を現したのは、ディエゴとベルムデスの二人であった。
「トゥパク・アマル様、お呼びでしょうか」
そう言いながら大股で部屋に入ってくるディエゴは、今日の戦闘で、顔面を縦断する生々しい切り傷を負い、その傷口からは、まだ赤黒い血がじっとりと滲んでいる。
ただでさえ厳(いかめ)しい彼の風貌に、その生傷は鬼気迫る凄みを与え、味方であっても射竦められそうなほどの気迫があった。
一方、既に老齢のベルムデスさえも、その肌の随所に切り傷を負い、しかも、右腕には厚く包帯を巻いて、痛々しげな戦闘の後遺症が見てとれる。
トゥパク・アマルは机上の書類一式を手にすると、二人を中央の重厚なテーブルに座らせ、自分もそちらに移動した。
「二人とも、突然、呼び出してすまなかった」
いつものように静かな低い声で言うトゥパク・アマルのその口調に、だが、何か非常に深刻なものの宿っていることを、この重側近二人は鋭く察知する。
トゥパク・アマルの副官にも等しきディエゴ、そして、トゥパク・アマルが全幅の信頼を置く相談役ベルムデス…――その二人のみが呼ばれている状況からも、何か、とても内密で、重要な用件が伝えられるであろうことを察し、ディエゴもベルムデスも、緊張の混じった、かなり真剣な面持ちになっている。
そんな二人に、トゥパク・アマルは瞳で深く頷く。
「ディエゴ。
わたしの右腕として、そなたには、この後のために、特に心しておいてほしいことなのだ。
そして、ベルムデス殿。
あなた様にまで、ご足労頂き、かたじけなく思います。
ですが、あなた様は、わたしの父の代から、我がインカ一族を支えてきたお方。
此度の件、共に、知っておいて頂きたい」
彼は、相変わらず静かにそう言うと、先ほどの書状と封筒をテーブルの上に乗せた。
「え?
書状ですか?!
このような時に?」
驚いたような眼差しでトゥパク・アマルの顔を見据えるディエゴに、当のトゥパク・アマルは、ただ、書状を二人の前にスッと滑らせるように近づけ、広げていく。

そして、低く響くあの声で、一語、一語、噛み含めるように言う。
「今から、この書状を送る手はずをとる。
この書状は、近い将来、我々インカの命運を左右する可能性のあるものだ。
それ故、そなたたちには、この内容を熟知しておいてもらいたい」
そう言いながら二人の前に書状を全て広げると、そのままトゥパク・アマルは腕を組み、まるで瞑想状態にでも入るがごとくに、椅子にもたれたまま、じっと瞼を閉じた。
そのトゥパク・アマルの様子に、ディエゴはそれ以上は何も問うことができず、訳が分からぬという眼差しで、しかしながら、ともかくも書状に目を通しはじめる。
ベルムデスも、まだ事態の流れに戸惑いつつも書状に視線を向けかけて、ふと傍の封筒に目が留まった。
彼の視線は、そのまま自然に、宛名をなぞっていく。
そして、ハッと大きく息を呑む。
「!!」
ベルムデスの目が、突如、カッと見開かれた。
「トゥパク・アマル様…まさか…!」
不意に叫ぶような声を発したベルムデスの横で、書状に目を通しかけたディエゴも、「うっ…な…!!」と、同様に、驚愕と混乱の呻き声を上げた。
彼のその目が、わななきながら、引きつるように大きく見開かれていく。
咄嗟、二人の視線は、トゥパク・アマルの方に走った。
だが、その二人の正面に座したまま、トゥパク・アマルは、ただ黙って瞼を閉じている。
ディエゴとベルムデスは衝撃の面持ちで、暫し、互いの顔を見合わせていたが、次の瞬間には、まるで喰らいつくがごとくの勢いで書状に目を通しはじめた。
今、書斎の中は、恐ろしく、静まり返っていく。
その静けさの中に、ディエゴのものとも、ベルムデスのものともつかぬ、いや、恐らく両者のものだろうか、深い溜息の漏れる音がする。
暫し、時の流れるのを見計らって、トゥパク・アマルが、その目をゆっくりと開けた。
彼の視界の中に、驚愕の眼のままに、呆然と己の方を見やっているディエゴとベルムデスの姿が映った。
二人とも、完全に声を失ったように、ただ、喰い入るようにこちらを見据えている。
にわかには、到底、信じられぬ…――!!という眼差しであった。
だが、それと同時に、老賢者ベルムデスの表情の中には、はやくも、どこか深い次元で合点のいったような色が浮かびはじめている。

トゥパク・アマルは、変らぬ静かな動作で、それら書状一式を己の手元に集めていく。
「驚かせたかもしれぬ。
だが、この期に及んでは、これも秘策。
そして、時を過(あやま)てぬ。
するなら、今だ。
だが、このことが下手に兵や民の間に流れれば、大きな誤解と混乱のもとともなりかねぬ。
それ故、二人だけに打ち明けたのだ」
きわめて沈着な声ながらも、有無を言わさぬ気迫を込めた口調でそう言うと、未(いま)だ、言葉を放てずにいる二人に、トゥパク・アマルはゆっくりと頷いた。
「そなたたちには、このことの意味も、わたしなりの考えも、誤解無きよう説明しておきたい。
この件について疑問があれば、何なりと、今、ここで聞いてくれ」
そんな、トゥパク・アマルに、やはり、にわかには言葉を発せられぬ二人であった。
トゥパク・アマルは、静かに待っている。
やがて、息を詰めたままの二人が、「ならば、恐れながら…」と、一つずつ謎解きをするがごとくに質問を投げはじめた。
トゥパク・アマルは、それらの問いに、丁寧に、彼なりの考えを説明していく。
かくして、その非常に内々の会合は、それから、かなり長い時間に渡って続けられた。
やがて、その秘密の会合を終えてから、トゥパク・アマルは再び階下の司令本部へと下り、そのまま屋外へ出て負傷兵たちの治療場へと向かった。

彼は、収容された瀕死の負傷兵たちが横たわる中に自ら入り、その身を屈めて、そっと一人一人に声をかけて回る。
もはや彼の表情は、憤怒も、悲痛さも、よもや能面のようなあの脱感情の状態をも凌駕し、今は、ただもう、深き慈愛を宿した眼差しになって、兵たちに己の手のぬくもりと労(いた)わりの視線を注いでいく。
一方、その頃、コイユールは、トゥパク・アマルの館である本部の入り口にいた。
そんな彼女の前に立つ、門前の警護兵たちは、すっかり閉口した表情である。
「トゥパク・アマル様はお忙しいのだ。
この非常時に、何を言っているのだ!
時期をわきまえなさい!!」
そんなふうに、己を叱ったり、逆に、宥(なだ)めすかしたりしている警護兵たちに、だが、コイユールは喰い下がる。
「無理なお願いだとは、わかっています!!
だけど、どうか一目(ひとめ)だけでも、トゥパク・アマル様に会わせてください…!
どうしてもお伝えしたいことがあるのです!!
どうか……!!」
警護兵たちに縋(すが)り付くようにしているコイユールの様子は、かなり常軌を逸している。
完全に顔色を失った鬼気迫る面持ちで、髪振り乱し、涙を流しながら、「トゥパク・アマルに会わせろ」と、うわ言のように訴え続けるその様子に、警護兵たちは、ますます警戒心を募らせた。
コイユール自身も、トゥパク・アマルに会って、それにどれほどの意味があるのか、もはや冷静になど考えられてはいなかった。
しかし、何か、非常に不吉なことが迫っている…――それを天が示している、最大限に行動に注意してほしいと、どうしてもそれを伝えなくてはならないと、その一念に憑かれていた。
他方、あまりのしつこさに、警護兵は、ついにコイユールの肩を掴んだ。
そして、「自分の持ち場に戻りなさい!!」と強く叱責し、扉近くから外へと彼女の体を強引に押し出す。
その瞬間、その華奢な体のどこにそんな力があったのかと驚くほどの強い力で、コイユールは警護兵の腕を振り払い、相手を激しく突き飛ばすと、そのまま一直線に館の中へと走り込んでいった。
だが、とうとう堪忍袋の緒が切れて、いや、むしろこのような非常時に一義勇兵に勝手な行動をされるわけにはいかぬ警護兵は、相当に険しい眼になると、大股でコイユールを追って館の扉の中に入った。
そして、驚いている本部の兵たちの目も構わずにトゥパク・アマルの姿を懸命に探しているコイユールを、背後から捕まえ、やむを得ぬという表情と共に、彼女のみぞおちに一撃を入れた。
そのまま、コイユールは、あっさりと気絶して意識を失った。
その頃、当のトゥパク・アマルは、負傷兵たちを力づけながら、まだ治療場の中にいた。
そんなトゥパク・アマルの傍に、先程の会合を終えて一旦別れたばかりのディエゴが、再び近づいた。
しかも、ディエゴは、今ひとたび、ひどく血相を変えている。
あの顔面を縦断する生傷からは、相変わらず赤黒い血が滲んでおり、その凄みのある形相に加えて、今、激しく眼を血走らせながら迫り来るそのさまには、さすがのトゥパク・アマルも息を詰めた。
トゥパク・アマルは、声を低めて問う。
「何事か。
先ほどの件で、まだ、何かあるのか?」
「いいえ。
先刻のこととは、全く別件で…!」
ディエゴはその目をカッと見開き、ズイッと身を寄せた。
そして、周囲の他の兵たちに聞こえぬよう、耳元で、慎重に、低く、太く、囁く。
「トゥパク・アマル様、ご報告せねばならぬことが…。
フランシスコ殿のお姿が、見えないのです!!」
「…――!」
トゥパク・アマルは、負傷兵に手を添えたまま、ディエゴの顔に釘付けられた。
ディエゴは深刻な眼差しで眉間に皺を寄せたまま、無言で、深く頷く。
トゥパク・アマルは、己の手を添えていた負傷兵にもう一度向き直り、「十分に、体も心も休まれよ」と真摯な声で語りかけると、ディエゴと共に、負傷兵の集団から抜け出ていった。

そして、二人は柱の陰に身を隠すようにして、素早く言葉を交わす。
「フランシスコ殿のお姿、いつから見えぬのだ?」
「戦場にて、昼間、見かけた者がおりましたが、それからは、どの者も見かけた記憶が無いと」
「まだ戦場には出ぬようにと、あれほど申しておいたのに…――!
しかも、此度の戦闘は、いつにも増して激しきもの。
なんと無謀な……!」
最後は呟くように言うと、トゥパク・アマルは、険しくも、激しく案じる色を浮かべ、鋭く遠くを見据える目になった。
ディエゴも、非常に厳しい表情で固唾を呑み、そして、唸(うな)るように言う。
「フランシスコ殿とて、今回の決戦が重要なことを存じていらしたから、焦っておられたのでしょう。
ご無理をして戦場に出て…お命を…、いや、もしや…、今頃、敵の手に:…――!!」
ディエゴの言葉が終わるのを待たず、トゥパク・アマルの表情は既に不穏に深く曇り、その目はひどく苦しげになる。
「ただちに周辺に兵を放ち、フランシスコ殿が、あるいは、負傷にて倒れてはいまいか、巡視に行かせよ」
「はっ!!」
ディエゴは一礼すると、飛ぶように立ち去った。
その後ろ姿を目で追いながら、トゥパク・アマルは、心底から祈らずにはおられない。
(フランシスコ殿、どうか、御身がご無事であらんことを…――!!)

かくして、その頃、夜闇に佇むスペイン軍の陣営では、トゥパク・アマルらの懸念の通り、昼間の戦闘中に捕えられ捕虜とされたフランシスコが、あの悪魔の化身のごとくのスペイン軍総指揮官アレッチェの元に引き出されていた。
フランシスコは両手を後ろ手に縛り上げられてはいたが、まだ、何も具体的な拷問も、暴力も、加えられてはいなかった。
しかし、アレッチェをはじめ、将軍バリェや、複数のスペイン軍幹部たちの、険しく、冷徹な、あの蔑むような視線に晒(さら)されて、完全に怯え切り、震え、慄(おのの)いていた。
立っていることさえ難儀に見えるほどに手足を震わせ、まるで折れそうな柳のごとくに痩せ細った肩と首をうなだれ、顔面を蒼白にしながら、恐れに目元をわななかせている。
その眼前のインディオ――正確には、インカ族とスペイン人との混血だが――を、アレッチェはむしろ唖然として、見下ろしていた。
トゥパク・アマルの側近に関しては既に情報収集をしていたため、この眼前の男が、トゥパク・アマルの側近であるばかりか、義兄弟でさえある、との調べもついている。
だが、そんなアレッチェは、あまりに脆弱なフランシスコの様子に、「己の持つ情報が誤っているのでは?」と、疑うほどに、驚き、呆れ返っていた。
そんな想念にアレッチェが憑かれている間にも、フランシスコの呼吸はいっそう不規則に乱れ、顔面からは脂汗が噴出しはじめている。
アレッチェは冷酷に目を細め、長い足で仁王立ちになったまま、その必要もないかと思いながらも、懐から拳銃を取り出した。
彼のその動作だけで、もうフランシスコは立ち上がっていることさえできず、その場に崩れるように、地に膝をついた。
全く信じられぬという冷え切った視線が、アレッチェのみならず、バリェ将軍、その他のスペイン軍幹部から注がれる。
アレッチェは銃を構えることもなく、無機質な、やや疑いさえ孕(はら)んだ声で問う。
「おまえは、トゥパク・アマルの側近フランシスコで、相違あるまいな」
何かに打たれたように身を固めるフランシスコに、アレッチェは辟易した目線を投げながら、その反応をじっと確かめる。
極度の戦慄からであろう、今や震えを通り越して、明らかに痙攣状態を呈しはじめたフランシスコは、よもや言葉も失ったのか、アレッチェの問いに応えない。
アレッチェは、銃口を、相手の乱れ切った頭髪に当てて、語気を荒げる。
「質問に答えよ!」
反射的にビクリと身を縮めて、フランシスコが、震えているのか頷いているのかさえ分からぬほどの風体で、首を縦に振る。
(下衆が…――!)
アレッチェは内面で毒づくと、フランシスコの頭髪を掴んで、己の方にその蒼白な顔を向けさせた。
その憔悴し切った顔面全体からは、ますます脂汗が噴出し、黄色がかった虚ろな目からは、既に涙が滲んでいる。
片手でフランシスコの髪を掴んだまま、もう片手で銃口をフランシスコの眉間に当て、あの冷酷な声でアレッチェが言う。
「捕虜となったおまえを、今、ここで殺すのは容易(たやす)いが、まあ、急がずとも、おまえたちトゥパク・アマルの側近どもは、いずれ処刑される運命にある」
フランシスコの顔面を、軽蔑し切った目で見下ろしながら、アレッチェは、その口元に不気味な笑みを浮かべた。
「反逆者どもの軍勢が敗北するのは、もはや時間の問題だ。
互いにまともな戦略も無く、正面からぶつかり合うだけの白兵戦と化した今、火器で圧倒的に勝る我々が断然に有利なのは、野蛮な原住民の、おまえの弱い頭でもわかろうというもの。
どちらにしろ、トゥパク・アマルは捕えられる。
これほどまでの甚大な被害を出した反乱の首謀者どもだ。
その罪状の重さは、計り知れぬ。
挙句、トゥパク・アマルのインカ一族も、側近も、一網打尽にされる。
たとえ地の果てに逃げようとも、一生、逆賊として、追われ続けるのだ。
もちろん、こうして既に捕虜になったおまえなどは、一番手で処刑になる。
しかも、トゥパク・アマルの重側近であるほど、あっさりと死ねる方法では殺してはもらえぬ。
ニ度とこの国で、このような反乱行為などを目論む謀反人が現われぬよう、その見せしめとして、数々の拷問の末、衆目の面前で、苦しみ抜く方法で処刑されるのだ」
アレッチェの冷ややかな視線の下で、フランシスコは、あまりの震撼から意識朦朧として目の焦点も定まらず、もはや話が聞こえているのかさえ定かではない。
その様子に、さすがのアレッチェも訝(いぶか)しむ。
(この者、もとから正常ではないのか?
何かの病気か?)
アレッチェは、その長身のガッシリとした体をゆっくりと屈(かが)め、フランシスコの目の高さになった。
黒髪に縁取られた、いかにも西洋人らしい彫りの深い横顔で、偏見と侮蔑に満ちた黒い瞳が獰猛な光を強める。
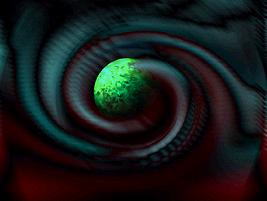
「ならば、話も通じやすいか」
今、フランシスコを隅々まで観察しながら独り言のように呟く彼の頭の中では、この捕虜の「利用方法」について、当初の人質としてのものから、もっと別の方法へと動きはじめていく。
アレッチェはフランシスコの頭髪を掴んだままに、しかし、相手の眉間から銃口をはずして、今度は親和的な笑みを浮かべた。
そして、恐怖の底に自ら嵌(はま)りこんでいる眼前の捕虜の顔を覗く。
「トゥパク・アマルの義兄弟とまで言われるおまえであれば、そのおまえを人質として立て、トゥパク・アマルに我が軍の要求を呑ませることもできようかと思ってはいたが…。
どうも、その目論(もくろ)みでは、事は上手くは運ばぬかもしれぬな。
この、見るからに、戦(いくさ)にも、何にも、全く役に立ちそうのないおまえなど、いかに、あの偽善者ぶったトゥパク・アマルとて、とうに愛想を尽かしていることであろう。
今頃は、足手まといを厄介払いできたと、あの男も、内心、喜んでおるかもしれんぞ」
「!!」
意識の混濁したような表情で、己の話など聞こえていないようにさえ見えていたフランシスコの虚ろな目に、だが、この時ばかりは、明らかに激しい衝撃の色が走ったのを、アレッチェは決して見逃さない。
アレッチェは、この男の急所はそこか、と、冷たく鼻で笑うと、さらに続ける。
「ふ…図星か。
あのトゥパク・アマルのこと、あからさまには、そのような素振りは見せなかろうが、結局のところ、おまえは冷遇されていたというわけか」
「……!!」
アレッチェは、フランシスコの反応の一つ一つを漏らすところなく観察しながら、あの不気味な笑みを湛えたまま、弄(もてあそ)ぶようにして相手の心を突き崩していく。
その目の前で、フランシスコは、強烈な連打を蒙(こうむ)った後のごとくに茫然自失し、表情は完全に生気(せいき)を失っている。
アレッチェは、その捕虜の死んだ魚のような目を、斜め上から睥睨(へいげい)するように見下ろした。
そして、フランシスコの頭髪を掴んでいた手を無造作に放すと、いかにも汚らわしいものに触れてしまったとばかりに、あらさまにその指を振った。
「もはや人質としてさえ利用価値の無いおまえなど、結局、生かしておく意味も無い。
……――だが、そんなおまえでも、生かしておいても良い条件が、たった一つだけある」
そこまで言うと、アレッチェはわざとらしく言葉を切って、唇の端を吊り上げる。
一方、フランシスコは、呆然とした様子は変らぬものの、そのアレッチェの言葉に、僅かに身を乗り出した。
その様子を観察しながら、アレッチェが再び口を開く。
「フランシスコ、ここは相談だ。
この国の、平和と秩序を回復するために、我々はおまえの力を本気で必要としている。
ここで力を貸してくれれば、この後、おまえは真に英雄として国中の民から崇められ、当然の結果として、完全なる安寧の生活が生涯に渡って、いや、それどころか、子々孫々の代まで保障されるであろう」
ガラリと色味を変えて語りかけてくる相手の口調とその内容に、朦朧としながらも、まだ微かに残る己の意識をつなぎとめるようにして、フランシスコは激しい混乱の眼でアレッチェを見上げた。
アレッチェは不遜な笑みを湛えたまま、ゆっくりと頷き返す。

「トゥパク・アマルを生け捕りにするために、おまえの力を貸してはくれまいか」
「!!!」
さすがのフランシスコも愕然として、「まさか…そのような……!」と、擦れた声を漏らす。
アレッチェは銃を地に降ろすと、代わりに、その手でフランシスコの頭を、輪郭をなぞるようにして、ゆっくりと撫でた。
「おまえをこのような状態まで追い込んだのは、誰だ?
あの男であろう。
そのトゥパク・アマルは、所詮は己が皇帝に返り咲きたいだけなのだ。
あいつは、人の心を操るのが上手い。
だから、おまえも騙(だま)され、これほどまでに、やつれて気の毒なことだ。
おまえと同じように、この国中の民が、あの者に騙され、踊らされているのだ。
ましてや、おまえは、半分はスペイン人の血。
仮に、万が一にも、あの者どもが天下を取ろうものなら、そこは野蛮なインディオの国。
スペイン人としての気高い血をも引くおまえに、今更、そんな土臭い世界での生活は耐えられまいよ。
なあ、フランシスコ…。
トゥパク・アマルのことだけでなく、他の側近どものことも思い出してみよ。
おまえは、本当に奴らに必要とされていたか?
トゥパク・アマルの側近どものことは、全て調べがついている。
例えば、ディエゴ、ビルカパサ、オルティゴーサ…――そして、あの青二才のアンドレスにすら、おまえは舐(な)められてきたのではあるまいか?
そんな奴らが天下を取ったらどうなる?
その暁には、むしろスペイン人に似た混血で、ひ弱なおまえの居場所など、あの者たちの中には、どこにもありはすまい。
おまえ自身、今までも、そのような危機感を抱いてきたのではあるまいか?
おまえには、奴らのつくるような野蛮な国ではなく、もっと西洋文化の香り高い、紳士的で、理知的な世界こそが似合っているのだ。
我々スペイン人が、スペイン本国や、この地に敷いてきた治世のような、そんな世界こそが、本来のおまえの居場所なのだ。
それを己の手で壊そうとするなど、おまえもトゥパク・アマルの傍にいて、ずいぶんと目を眩(くら)まされたものだ。
おまえは、おまえ自身で、己の首を絞めてきたのだ。
だから、この反乱が起こってからは、恐らく、おまえにとっては、さぞ苦悩の連続であったことだろうよ」
すっかり心を見透かされたように己を見上げるフランシスコに、アレッチェは、勝ち誇ったように、ほくそえむ。
フランシスコの痙攣する瞼の奥で、わななくように収縮を繰り返す瞳の中には、激しい衝撃の色と共に、否、それ以上に、ついに理解者を得た!!…――とばかりの、深層意識から突き上げる強い恍惚が滲みはじめる。
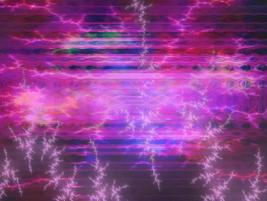
アレッチェは、普段の彼を知る周囲のスペイン兵たちから見ても寒気が走るほどに、その目尻から笑みを垂れ流しながら、痩せたフランシスコの肩を両手でガッチリと掴んだ。
一方、フランシスコは、その衝撃と恍惚の眼で、もはや、人形のように、アレッチェのなすがままになっている。
アレッチェは、既に「フランシスコ」という格好の道具を手中に入れたことを確信しながら、噛み含めるように、低い声で続けた。
「おまえなら、話が通じるようだ。
トゥパク・アマルに、おまえのような側近がいてくれたことは、我々にとっても、この国にとっても、全くの救いであったと思わずにはおられぬ。
こうして我々が出会ったのも、運命。
おまえの本当の力を発揮する時が来たのだ。
フランシスコ…この国の真の平和と秩序を回復するために、おまえの力を貸してほしい。
おまえの居場所は、我々の元にこそ、あるのだ。
繰り返して言う。
謀反人トゥパク・アマルを生け捕りにするために、おまえの力を貸してくれ。
もちろん、具体的な保障も約束する。
もともとトゥパク・アマルの身柄には、2万ペソ(註:邦貨に換算して約1千万円)もの報奨金を賭けている。
その額に、さらに上乗せして、おまえに全て渡そう。
それほどの大金があれば、この国でなら、我らスペイン側の庇護のもと、おまえ自身はもとより、子々孫々の代まで、何不自由無く暮らしていくことができよう。
他にも、おまえが望むことがあれば、全て叶えよう。
これら全ての見返りは、副王と共にこの国を統(す)べる、全権植民地巡察官たる、このわたしが保証することだ。
それほどの見返りに値するほど、おまえの協力は、この国の将来のために重要なのだ。
これは、正義のためなのだ!
フランシスコ…――おまえの、真の居場所は、我らの元にこそある!!
今こそ、おまえの力が必要なのだ!!」
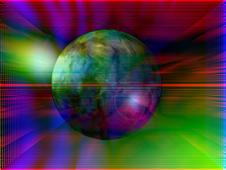
あまりの激しい展開の連続に、既に、フランシスコの意識は事切れかけていた。
だが、次第に遠のく意識の中で、フランシスコは、アレッチェの最後の言葉をじっと聞いていた。
『フランシスコ、おまえの真の居場所は、我らの元にこそある!!
おまえの力が必要なのだ…――!!』


